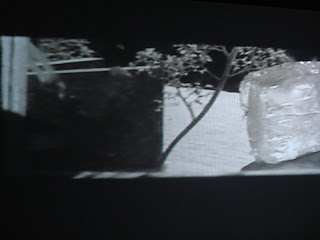先週の金曜日、表千家ゆかりの茶懐石の名店、「柿傳」(@新宿)で
ランチをしました。
川端康成の直筆
「柿傳の茶席は東京に一つの名物となるでせう」
という言葉を川端康成は残しています。
表千家家元而妙斎御銘「松の翠」(純米大吟醸、伏見)
ガラス杯に注いだ瞬間から甘い芳香が立ち昇るほど、芳醇な銘酒。
透明度がきわめて高く、梨のようなフルーティーな香りと甘みがあり、
ひとくち口に含むだけで、うっとりとした幸せな気分が体じゅうに広がります。
夏にぴったりの、清涼感のある美味しいお酒でした。
二合目は、山口県旭酒造の「獺祭(だっさい)」(純米大吟醸)。
こちらも山田錦を50%まで磨いた、非常に香り高い美酒でした。
先付:(右)寄せ無花果(いちじく)、モロコシ味噌
(左)鱧皮、胡瓜(大葉、胡麻、生姜酢)
寄せ無花果とは要するにイチジクのゼリー寄せ。
鱧皮は、コラーゲンたっぷりなのが嬉しい(笑)。
向付:鯛と縞鯵
これ、すっごくおいしかったです。お酒が進むのなんのって……。
弦楽器(琵琶?)の向付皿が夏の怪談を連想させます。
ちょっとした遊び心ですね。
煮物椀:海老入枝豆真蒸、雲丹素麺、椎茸、柚子
茶懐石のメインディッシュにあたるのが煮物椀。
亭主が最も心をこめ、料理人が最も力を入れる一品です。
御出汁は京風の上品な味でとても美味しかったです。
(ただ、ウニの味も香りもしない雲丹素麺は美観的にも
ないほうがよかったかもしれません。)
焼き物:福子柚庵焼、青唐、山桃
福子は、出世魚である鱸の稚魚で、おめでたい魚らしいです。
脂がほどよくのっていて、焼き加減も完璧でした。
揚物:鱧紫蘇揚、苦瓜二身揚、れんこん梅肉揚、赤ピーマン
炊合せ:南瓜、茄子揚煮、身欠にしん、オクラ
ご飯、香の物、汁(焼目付湯葉、粉山椒)
香の物は、これも京風の薄味でわたし好みでした。
柿傳特製の紅白干菓子(「柿」の字の印)と御薄
抹茶は小山園の「和光」で、とても甘みがありました。
茶碗は角筈(つのはず)焼で、片岡哲という作家さんのもの。
角筈焼とは、ここ新宿、柿傳角筈窯で焼かれた焼き物のことだそうです。
(新宿の土で焼いたのでしょうか?)
琴の調べが流れる落ち着いた店内。
新宿(駅から徒歩1分)とは思えない静けさのなか、美味しいお食事と
お酒、そしてお茶をゆったりと堪能した至福のひと時でした。
2010年8月12日木曜日
建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション展
最近、建築系のビジュアル本を翻訳したこともあり、先週の日曜日、東京国立近代美術館で開催されていた『建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション』展に出かけた(この日は最終日)。
展覧会のタイトル「建築はどこにあるの?」は来館者への問いかけ。各自が7つのインスタレーションに触れるなかで、その答えを見つけていくという趣向らしい。
パンフレットに「あなたの答えを写真におさめよう!」とあるように、写真は撮り放題。デジカメ片手に撮りまくったおかげで、ただ見るよりも違った形で楽しめた展覧会だった(一眼レフを手にした若い女性も多かった)。
中村竜治『とうもろこし畑』
紙でできたこの構造物。ちょうどトウモロコシ畑の高さに作られていて、
見る角度によって「向こう」の見え方が変化していく。
北海道の大草原に「カフェ」として設計された建築の3分の1の模型。草原の両側に「どこかにつながっていそうな」扉が開いている、という構成。
鈴木了二『物質試行51 DUBHOUSE』
建築家いわく、「『DUBHOUSE』は何処にでも行ける建築」であり、
「事物の境界を揺さぶり、輪郭線を消す」。
内藤廣『赤縞』
赤いレーザーに刻まれた暗い空間を通っていく。
そうすることで、「人間が動くことで『空間』が生まれることに
気づくのではないか」と建築家は言う。
いつもは見えていない空間の抽象性を体感するための装置だそうだ。
菊地宏『ある部屋の一日』その1
ちょっと分りにくいかもしれませんが、中央にあるのが部屋の内と外の模型。
その周りをカメラがライトで照らしながら回っています。
(太陽の一日の運行を模しているそうです。)
菊地宏『ある部屋の一日』その2
ライトに照られれた部屋の内と外の模型。
そのカメラがとらえた映像が、次の展示室で映写されている。
菊地宏『ある部屋の一日』その3
このような二重の仕掛けによって、「自然光の入らない空間で、
自然光をテーマにする」という難題を作品化することに成功した。
そのアイデアに脱帽!
映像に対面する形でベンチが並べられていたので、
縁側でゆったりと庭を眺めているような気分を味わうことができた。
伊東豊雄『うちのうちのうち』
現在進行中のプロジェクト「今治市伊東豊雄建築ミュージアム」の
約2分の1のスケール。
つまり、「美術館のなかにもうひとつの美術館」をつくったのが、
今回の作品『うちのうちのうち』だ。
垂直の柱や壁がまったくない、多面体の構造物となっている。
アトリエ・ワン『まちあわせ』
キリンとゾウとカバさんと美術館の前で待ち合わせ、という楽しい作品。
なぜかクマさんも展示されていた。これがいちばん気に入った!?
……結論、建築はどこにもなかった。
展覧会のタイトル「建築はどこにあるの?」は来館者への問いかけ。各自が7つのインスタレーションに触れるなかで、その答えを見つけていくという趣向らしい。
パンフレットに「あなたの答えを写真におさめよう!」とあるように、写真は撮り放題。デジカメ片手に撮りまくったおかげで、ただ見るよりも違った形で楽しめた展覧会だった(一眼レフを手にした若い女性も多かった)。
中村竜治『とうもろこし畑』
紙でできたこの構造物。ちょうどトウモロコシ畑の高さに作られていて、
見る角度によって「向こう」の見え方が変化していく。
中山英之『大草原の大きな扉』
北海道の大草原に「カフェ」として設計された建築の3分の1の模型。草原の両側に「どこかにつながっていそうな」扉が開いている、という構成。
鈴木了二『物質試行51 DUBHOUSE』
建築家いわく、「『DUBHOUSE』は何処にでも行ける建築」であり、
「事物の境界を揺さぶり、輪郭線を消す」。
内藤廣『赤縞』
赤いレーザーに刻まれた暗い空間を通っていく。
そうすることで、「人間が動くことで『空間』が生まれることに
気づくのではないか」と建築家は言う。
いつもは見えていない空間の抽象性を体感するための装置だそうだ。
菊地宏『ある部屋の一日』その1
ちょっと分りにくいかもしれませんが、中央にあるのが部屋の内と外の模型。
その周りをカメラがライトで照らしながら回っています。
(太陽の一日の運行を模しているそうです。)
ライトに照られれた部屋の内と外の模型。
そのカメラがとらえた映像が、次の展示室で映写されている。
菊地宏『ある部屋の一日』その3
このような二重の仕掛けによって、「自然光の入らない空間で、
自然光をテーマにする」という難題を作品化することに成功した。
そのアイデアに脱帽!
映像に対面する形でベンチが並べられていたので、
縁側でゆったりと庭を眺めているような気分を味わうことができた。
伊東豊雄『うちのうちのうち』
現在進行中のプロジェクト「今治市伊東豊雄建築ミュージアム」の
約2分の1のスケール。
つまり、「美術館のなかにもうひとつの美術館」をつくったのが、
今回の作品『うちのうちのうち』だ。
垂直の柱や壁がまったくない、多面体の構造物となっている。
アトリエ・ワン『まちあわせ』
キリンとゾウとカバさんと美術館の前で待ち合わせ、という楽しい作品。
なぜかクマさんも展示されていた。これがいちばん気に入った!?
……結論、建築はどこにもなかった。
ダブルスピークの絵画とスキタイの羊、あるいはマンドラゴラの根
(東京国立近代美術館のつづき)
この日は2時前に着いたのだが、タイミング良く、所蔵作品展のガイドツアーが始まったので参加させてもらった。テーマは「大画面作品の見方」。最初の作品は、川端龍子の『草炎』だった。
濃紺地の大画面に金泥で描かれた草花は、まるで蒔絵のようにも見える。
同じ金泥でも、銀を混ぜて白っぽい色合いを出したり、金の純度を下げて透明感を出したりと、微妙な変化を加えることで、装飾性と写実性の見事なバランスが生み出されている。
当初、洋画家だった川端龍子は渡米した際、ボストン美術館で目にした日本美術に感銘を受けて、日本画家に転向する。この精緻な写実性は、彼の洋画家時代の技術が生かされているのだろう。江戸琳派風のこの絵は、金を用いても決して華美にはならず、しっとりと落ち着いた風情を醸していた。
次にガイドさん(大内久美子さん)に案内されたのは、福沢一郎の『牛』だった。
大画面なので、まずは参加者一同、遠くからこの絵を眺め、ガイドさんから「どんな印象を受けますか?」などの質問を受ける。
どこか歪(いびつ)な印象の絵だ。牛は短足で不格好で、ところどころ穴があいているし、肉にしまりがなく、どこか不気味である。背後では、人が、意味もなく折り重なっているのだろうか。どんよりとした雲。荒涼とした大地に太陽が容赦なく照りつけている。
1930年代半ば、当時絵が売れなかった福沢(彼は最初、朝倉文夫に師事した彫刻家だったが、のちに洋画家に転向した)は、心機一転満州に渡る。日本とはあまりにも違う満州の風土、人々、町並み。そこからインスピレーションを得て描いたのが、この絵だという(牛は、古代ギリシャの壺絵のモチーフを参考にしたそうだ)。
三番目にガイドさんに案内されたのが、大岩オスカールの『ガーデニング(平和への道)』。
遠くから見た『ガーデニング』。タイトルと絵がしっくりこない。
ここでも、先ほどと同じように、まずは離れて大画面の作品をみんなで眺めた。廃墟のような街並みが画面の左右に広がり、中央に河らしきものが描かれている。白く散らばっているのは、花だろうか。
近づいてみると、戦車らしきものが見える。911事件後のイラク戦争を描いた作品だそうだ。作者は40代の日系ブラジル人、気鋭の画家だ。サブタイトルの『平和への道』というのは、アメリカがこの戦争で使った大義名分。つまり、非常にアイロニカルな絵であり、白い花のように見えたものは、場所によっては白い硝煙となっている。
「平和のための戦い」という、ジョージ・オーウェルの小説『1984年』に出てくるダブルスピーク(「戦争は平和である」という党のスローガン)という自家撞着を絵画化したような作品だ。だが、これは小説の中の出来事ではなく、現に今も起きていることであり、それを世界が許容し、日本が支援している。この絵を見ることで、そういう現実をあらためて考えさせられた。
最後に案内されたのが、野見山暁治の『ある証言』だった。
「なんじゃこりゃあ!」という感じ。いつものように「これ、何に見えますか?」というガイドさんの問いかけに、「クエのような巨大魚があおむけになって大口を開けているところ。背景は海かな」と、適当に答えたわたし。他には、「大きながまぐち」とか、「まな板の上に載せられた魚」などの意見があった。
実はこれ、大きな壷を上から見た絵だとのこと。 嵐の日にベランダでぐらぐら揺れていた大壺が、ある瞬間にパンッと粉々に割れた、その衝撃を絵にしたそうだ。よく分らないけれど、嵐っぽい雰囲気は漂っていた。92歳の野見山画伯は、今もこうした迫力のある絵を描いていらっしゃるそうである。 その生命力、あやかりたいものだ。
こんな感じで、美術館のガイドツアーに参加したのは初めてだったが、見ず知らずの人たちと一緒に、ああだこうだと感想を述べながら、ひとつの作品をじっくりと鑑賞するのは、とても楽しい経験だった。
ほかにも所蔵展には見ごたえのある作品がたくさんあった(ここは「カメラシール」を衣服に貼れば撮影可能。この美術館の、こういう太っ腹なところが好き)。
安田靫彦『挿花』
小林古径『茄子』
奥村土牛『胡瓜畑』
小倉遊亀『浴女 その二』
……と、涼しげな夏らしい展示が続きます。
安井曽太郎『奥入瀬の渓流』
安井曽太郎『金蓉』
香月泰男『釣り床』
大好きな加山又造さんの『天の川』
いつ見ても、美しい絵です。
イケムラレイコ『樹の愛』
樹から人が生えているのか、人から樹が生えているのか?
澁澤龍彦の「スキタイの羊」あるいは「マンドラゴラの根(人の形をいていて、引き抜くと悲鳴のような声をあげるという)」を思い出す。
澁澤いわく、「ワクワク島では、イチジクに似た植物の果実から、羊ではなくて、人間の若い娘が生じるのである。果実が熟すると、娘は完全な肉体を揃えて、髪の毛で枝からぶら下がり、やがて熟し切ると、『ワクワク』という悲しげな叫び声をあげながら、枝から落ちて死んでしまう。哀切な童話的な幻想にみちた伝説と言ってよいだろう」。
こういう得体のしれない植物は見ているだけでワクワクします。
収蔵展以外にも、「いみありげなしみ」というタイトルの「(意味のある?)しみ」をテーマにした作品展もあった(つまるところ絵画を構成するのも、色彩や形状をもつ画面上の「しみ」にほかならない)。
北脇昇『デカルコマニーA』
この日は2時前に着いたのだが、タイミング良く、所蔵作品展のガイドツアーが始まったので参加させてもらった。テーマは「大画面作品の見方」。最初の作品は、川端龍子の『草炎』だった。
濃紺地の大画面に金泥で描かれた草花は、まるで蒔絵のようにも見える。
同じ金泥でも、銀を混ぜて白っぽい色合いを出したり、金の純度を下げて透明感を出したりと、微妙な変化を加えることで、装飾性と写実性の見事なバランスが生み出されている。
当初、洋画家だった川端龍子は渡米した際、ボストン美術館で目にした日本美術に感銘を受けて、日本画家に転向する。この精緻な写実性は、彼の洋画家時代の技術が生かされているのだろう。江戸琳派風のこの絵は、金を用いても決して華美にはならず、しっとりと落ち着いた風情を醸していた。
次にガイドさん(大内久美子さん)に案内されたのは、福沢一郎の『牛』だった。
大画面なので、まずは参加者一同、遠くからこの絵を眺め、ガイドさんから「どんな印象を受けますか?」などの質問を受ける。
どこか歪(いびつ)な印象の絵だ。牛は短足で不格好で、ところどころ穴があいているし、肉にしまりがなく、どこか不気味である。背後では、人が、意味もなく折り重なっているのだろうか。どんよりとした雲。荒涼とした大地に太陽が容赦なく照りつけている。
1930年代半ば、当時絵が売れなかった福沢(彼は最初、朝倉文夫に師事した彫刻家だったが、のちに洋画家に転向した)は、心機一転満州に渡る。日本とはあまりにも違う満州の風土、人々、町並み。そこからインスピレーションを得て描いたのが、この絵だという(牛は、古代ギリシャの壺絵のモチーフを参考にしたそうだ)。
三番目にガイドさんに案内されたのが、大岩オスカールの『ガーデニング(平和への道)』。
遠くから見た『ガーデニング』。タイトルと絵がしっくりこない。
ここでも、先ほどと同じように、まずは離れて大画面の作品をみんなで眺めた。廃墟のような街並みが画面の左右に広がり、中央に河らしきものが描かれている。白く散らばっているのは、花だろうか。
近づいてみると、戦車らしきものが見える。911事件後のイラク戦争を描いた作品だそうだ。作者は40代の日系ブラジル人、気鋭の画家だ。サブタイトルの『平和への道』というのは、アメリカがこの戦争で使った大義名分。つまり、非常にアイロニカルな絵であり、白い花のように見えたものは、場所によっては白い硝煙となっている。
「平和のための戦い」という、ジョージ・オーウェルの小説『1984年』に出てくるダブルスピーク(「戦争は平和である」という党のスローガン)という自家撞着を絵画化したような作品だ。だが、これは小説の中の出来事ではなく、現に今も起きていることであり、それを世界が許容し、日本が支援している。この絵を見ることで、そういう現実をあらためて考えさせられた。
最後に案内されたのが、野見山暁治の『ある証言』だった。
「なんじゃこりゃあ!」という感じ。いつものように「これ、何に見えますか?」というガイドさんの問いかけに、「クエのような巨大魚があおむけになって大口を開けているところ。背景は海かな」と、適当に答えたわたし。他には、「大きながまぐち」とか、「まな板の上に載せられた魚」などの意見があった。
実はこれ、大きな壷を上から見た絵だとのこと。 嵐の日にベランダでぐらぐら揺れていた大壺が、ある瞬間にパンッと粉々に割れた、その衝撃を絵にしたそうだ。よく分らないけれど、嵐っぽい雰囲気は漂っていた。92歳の野見山画伯は、今もこうした迫力のある絵を描いていらっしゃるそうである。 その生命力、あやかりたいものだ。
こんな感じで、美術館のガイドツアーに参加したのは初めてだったが、見ず知らずの人たちと一緒に、ああだこうだと感想を述べながら、ひとつの作品をじっくりと鑑賞するのは、とても楽しい経験だった。
ほかにも所蔵展には見ごたえのある作品がたくさんあった(ここは「カメラシール」を衣服に貼れば撮影可能。この美術館の、こういう太っ腹なところが好き)。
安田靫彦『挿花』
小林古径『茄子』
奥村土牛『胡瓜畑』
小倉遊亀『浴女 その二』
……と、涼しげな夏らしい展示が続きます。
安井曽太郎『奥入瀬の渓流』
安井曽太郎『金蓉』
香月泰男『釣り床』
大好きな加山又造さんの『天の川』
いつ見ても、美しい絵です。
イケムラレイコ『樹の愛』
樹から人が生えているのか、人から樹が生えているのか?
澁澤龍彦の「スキタイの羊」あるいは「マンドラゴラの根(人の形をいていて、引き抜くと悲鳴のような声をあげるという)」を思い出す。
澁澤いわく、「ワクワク島では、イチジクに似た植物の果実から、羊ではなくて、人間の若い娘が生じるのである。果実が熟すると、娘は完全な肉体を揃えて、髪の毛で枝からぶら下がり、やがて熟し切ると、『ワクワク』という悲しげな叫び声をあげながら、枝から落ちて死んでしまう。哀切な童話的な幻想にみちた伝説と言ってよいだろう」。
こういう得体のしれない植物は見ているだけでワクワクします。
収蔵展以外にも、「いみありげなしみ」というタイトルの「(意味のある?)しみ」をテーマにした作品展もあった(つまるところ絵画を構成するのも、色彩や形状をもつ画面上の「しみ」にほかならない)。
北脇昇『デカルコマニーA』
2010年7月28日水曜日
三菱一号館美術館:女らしさの文化史
ミュージアムショップの窓から見た丸の内のオフィス街。
外に出ると、日がとっぷり暮れていた。
(つづき)
第Ⅲ部は「マネとパリ生活」。
マネの作品以外にも、19世紀後半のパリの風俗をあらわす絵画や写真、建築物の円柱や柱頭の彫刻が展示されていた。
オペラ座やテュイルリー宮での仮面舞踏会をテーマにした作品も多く、そのなかでひときわ目を引いたのが、ジャン・ベローの『夜会』だった。http://www.slayers.ne.jp/~luke/winslow/cw240.jpg
絵に描かれた夜会の華やかさ、美しさは素晴らしく、しばしうっとりと見入ったが、やはり注目すべきは貴婦人たちの、コルセットによって異様なまでに締め付けられたくびれた腰だろう。 コルセットとコルセットによる人体への悪影響については、小倉孝誠の『女らしさの文化史』のなかで詳述されている(解説ではこのベローの『夜会』が、コルセットという風習の好例として紹介されている)。
蟻か蜂のようにくびれたこの腰は、絵画による誇張ではない。その証拠に同じコーナーに展示されていたアンリ・ルモワンヌの写真『競馬場、観客たち』にも、当時の美の基準に適うよう、腰を(拷問のごとく)人工的に締め付けられた女性たちの姿が写っている。
常々疑問に思っていたのだけれど、このコルセットで締め付けられた女性の腰は、コルセットを外した時も、かなり変形していたのではないだろうか。
この時期さまざまな裸婦像が描かれているが、わたしの知る限り、いずれもごく普通の、ナチュラルにくびれた腰の裸婦ばかりで、人工的に締め付けられた跡などはまったく見られない。 現在の(日本女性の)基準からすれば、当時のフランス女性はどちらかというと豊満なウエストをしていたように思う。 それをあれだけ不自然な形で締め付けるのだから(当時の小説などで気絶する女性やヒステリーの発作を起こす女性が多く登場するのは、コルセットのせいだという説もあるほど)、コルセットを外した場合、うっ血による痣ができていたり、変形していたりしてもおかしくはないはずだ。
それなのに変形した腰を描いた絵画を目にすることがあまりないのは、写実主義絵画の隆盛と時を同じくして、コルセットの文化が衰退していったからなのだろうか。
纏足(てんそく)を外した中国女性の足の写真を見たことがあるが、グロテスクに変形していて恐ろしいほどだった。時代とともに美の基準も変遷するとはいえ、あれをエロティックと感じるとは……(あくまで裸足ではなく、「小さな沓をはいた」足にエロスを感じたのだと思うが、それにしても沓のなかは膿みただれて悪臭を放っていたというから、人の美意識(ここまでくると、もはやフェティシズムというべきか?)というものは摩訶不思議である)。
昔、『ピアノレッスン』というオーストラリアの映画で、ヒロインがコルセットを脱がされていくシーンがあったが、これとてヒロインの裸体は、皺ひとつ、痣ひとつない、正常な裸体だった(映像の審美性からそうなったのかもしれないが。ちなみに、このヒロインを演じたホリー・ハンターって、マネの『オランピア』に似ていると思うのは、わたしだけ?)。
美術館の中庭は噴水もあって夕涼みにぴったり。
復元された昭和初期の趣のある建物。
三菱一号館美術館http://mimt.jp/
外に出ると、日がとっぷり暮れていた。
(つづき)
第Ⅲ部は「マネとパリ生活」。
マネの作品以外にも、19世紀後半のパリの風俗をあらわす絵画や写真、建築物の円柱や柱頭の彫刻が展示されていた。
オペラ座やテュイルリー宮での仮面舞踏会をテーマにした作品も多く、そのなかでひときわ目を引いたのが、ジャン・ベローの『夜会』だった。http://www.slayers.ne.jp/~luke/winslow/cw240.jpg
絵に描かれた夜会の華やかさ、美しさは素晴らしく、しばしうっとりと見入ったが、やはり注目すべきは貴婦人たちの、コルセットによって異様なまでに締め付けられたくびれた腰だろう。 コルセットとコルセットによる人体への悪影響については、小倉孝誠の『女らしさの文化史』のなかで詳述されている(解説ではこのベローの『夜会』が、コルセットという風習の好例として紹介されている)。
蟻か蜂のようにくびれたこの腰は、絵画による誇張ではない。その証拠に同じコーナーに展示されていたアンリ・ルモワンヌの写真『競馬場、観客たち』にも、当時の美の基準に適うよう、腰を(拷問のごとく)人工的に締め付けられた女性たちの姿が写っている。
常々疑問に思っていたのだけれど、このコルセットで締め付けられた女性の腰は、コルセットを外した時も、かなり変形していたのではないだろうか。
この時期さまざまな裸婦像が描かれているが、わたしの知る限り、いずれもごく普通の、ナチュラルにくびれた腰の裸婦ばかりで、人工的に締め付けられた跡などはまったく見られない。 現在の(日本女性の)基準からすれば、当時のフランス女性はどちらかというと豊満なウエストをしていたように思う。 それをあれだけ不自然な形で締め付けるのだから(当時の小説などで気絶する女性やヒステリーの発作を起こす女性が多く登場するのは、コルセットのせいだという説もあるほど)、コルセットを外した場合、うっ血による痣ができていたり、変形していたりしてもおかしくはないはずだ。
それなのに変形した腰を描いた絵画を目にすることがあまりないのは、写実主義絵画の隆盛と時を同じくして、コルセットの文化が衰退していったからなのだろうか。
纏足(てんそく)を外した中国女性の足の写真を見たことがあるが、グロテスクに変形していて恐ろしいほどだった。時代とともに美の基準も変遷するとはいえ、あれをエロティックと感じるとは……(あくまで裸足ではなく、「小さな沓をはいた」足にエロスを感じたのだと思うが、それにしても沓のなかは膿みただれて悪臭を放っていたというから、人の美意識(ここまでくると、もはやフェティシズムというべきか?)というものは摩訶不思議である)。
昔、『ピアノレッスン』というオーストラリアの映画で、ヒロインがコルセットを脱がされていくシーンがあったが、これとてヒロインの裸体は、皺ひとつ、痣ひとつない、正常な裸体だった(映像の審美性からそうなったのかもしれないが。ちなみに、このヒロインを演じたホリー・ハンターって、マネの『オランピア』に似ていると思うのは、わたしだけ?)。
美術館の中庭は噴水もあって夕涼みにぴったり。
復元された昭和初期の趣のある建物。
三菱一号館美術館http://mimt.jp/
聖女か悪女か:モリゾとムーラン
渡り廊下から見た美術館の中庭。
廊下の窓から見下ろしたカフェのある中庭。
(昨日のつづき)
第二部には、この展覧会の目玉でもあるベルト・モリゾをモデルにした作品がいくつか展示されていた。 いずれも黒衣のモリゾだが、印象はかなり異なる。
1868年(日本では明治維新が起きた年)、マネは、ルーブル美術館でルーベンスの模写をしていたモリゾに出会う。それから4年後に描かれたのが、、マネの最高傑作のひとつ、『すみれの花束をつけたベルト・モリゾ』http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=3774。 お嬢様育ちで、画才に恵まれたモリゾの、愛らしくも高貴なまなざしと、無垢で清らかな美しさを見事にとらえた作品だ。
帽子もドレスもスカーフも、全身黒ずくめで、黒を多用しているのにもかかわらず、斜めから射し込む光とモリゾの穏やかなみずみずしさのおかげで、暗さをみじんも感じさせない。それどころか、画面は夢や希望や生気であふれている。 あどけない表情で描かれているが、このときモリゾはすでに30代。 モリゾそのものの姿というよりも、画家がとらえた彼女の若々しく愛くるしい印象が描かれているのだろう。
実際、彼女自身の性格はどちらかというと、神経質で、しばしば鬱症状にも悩まされていたらしい。 そうした彼女の内面の奥深さや苦悩を垣間見ることができるのが、『扇を持つベルト・モリゾ』だ。http://www.fineartprintsondemand.com/artists/manet/berthe_morisot_holding_a_fan.htm『すみれの花束をつけた』からわずか2年後の作品だが、まさに黒衣の婦人というべき、憂いをたたえた大人びた表情で描かれている(このときモリゾは33歳なので、おそらくこちらの絵の方がモリゾ本来の姿に近いのかもしれない。ちなみにモリゾ自身は、同じく今回展示されていた『横たわるベルト・モリゾの肖像』を、「最も自分に似ている作品」と語っている)。
『すみれの花束をつけたベルト・モリゾ』はいつまでも見ていたくなるような素敵な絵だが、ややアンニュイな雰囲気を持つ『扇を持つベルト・モリゾ』のほうに、わたしはより魅力を感じるようだ。
マネとベルト・モリゾとの関係については、恋仲であったとか、いろいろ取り沙汰されているが、本当のところはどうだったのだろう。 マネにとってモリゾは大切な存在だったし、絵からも彼の彼女に対する慈愛の情が伝わってくる。
だが、どちらかといえば(これはわたしの勝手な想像であり、願望でもあるが)、モリゾはマネにとって愛おしくも、犯しがたい女性であり、画家としても尊敬すべき相手だったのではないだろうか。 二人の関係がプラトニックなものにとどまっていたからこそ、モリゾはマネの弟、ウジェーヌと結婚して幸せな家庭を築くことができたし、ウジェーヌも彼女の夫として、そしてモリゾの絵の最大の理解者として、結婚後も彼女の創作活動を応援し続けたのではないだろうか。
いずれにしろ、モリゾは裕福で満ち足りた家庭生活を送りながら、自分の姉や娘をモデルにした温かみのある作品を数多く残している。
いっぽう、マネが最も愛したもうひとりのモデル、ヴィクトリーヌ・ムーランも画家を志し、1876年にはサロンに入選するが、その後は酒に溺れ、困窮した生活を送ったという。 なんとなく「モンパルナスのキキ」ことアリス・プランを髣髴とさせるエピソードだ。 時代を切り拓いた芸術家のミューズたちの悲しい末路。 だからこそ、朽ちて滅びていく前のその煌めく姿を映しとった作品――画家が切り取ったモデルの人生の一瞬のかけら――には、名状しがたいある種の生命力のようなものが宿っているのかもしれない。 (つづく)
廊下の窓から見下ろしたカフェのある中庭。
(昨日のつづき)
第二部には、この展覧会の目玉でもあるベルト・モリゾをモデルにした作品がいくつか展示されていた。 いずれも黒衣のモリゾだが、印象はかなり異なる。
1868年(日本では明治維新が起きた年)、マネは、ルーブル美術館でルーベンスの模写をしていたモリゾに出会う。それから4年後に描かれたのが、、マネの最高傑作のひとつ、『すみれの花束をつけたベルト・モリゾ』http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=3774。 お嬢様育ちで、画才に恵まれたモリゾの、愛らしくも高貴なまなざしと、無垢で清らかな美しさを見事にとらえた作品だ。
帽子もドレスもスカーフも、全身黒ずくめで、黒を多用しているのにもかかわらず、斜めから射し込む光とモリゾの穏やかなみずみずしさのおかげで、暗さをみじんも感じさせない。それどころか、画面は夢や希望や生気であふれている。 あどけない表情で描かれているが、このときモリゾはすでに30代。 モリゾそのものの姿というよりも、画家がとらえた彼女の若々しく愛くるしい印象が描かれているのだろう。
実際、彼女自身の性格はどちらかというと、神経質で、しばしば鬱症状にも悩まされていたらしい。 そうした彼女の内面の奥深さや苦悩を垣間見ることができるのが、『扇を持つベルト・モリゾ』だ。http://www.fineartprintsondemand.com/artists/manet/berthe_morisot_holding_a_fan.htm『すみれの花束をつけた』からわずか2年後の作品だが、まさに黒衣の婦人というべき、憂いをたたえた大人びた表情で描かれている(このときモリゾは33歳なので、おそらくこちらの絵の方がモリゾ本来の姿に近いのかもしれない。ちなみにモリゾ自身は、同じく今回展示されていた『横たわるベルト・モリゾの肖像』を、「最も自分に似ている作品」と語っている)。
『すみれの花束をつけたベルト・モリゾ』はいつまでも見ていたくなるような素敵な絵だが、ややアンニュイな雰囲気を持つ『扇を持つベルト・モリゾ』のほうに、わたしはより魅力を感じるようだ。
マネとベルト・モリゾとの関係については、恋仲であったとか、いろいろ取り沙汰されているが、本当のところはどうだったのだろう。 マネにとってモリゾは大切な存在だったし、絵からも彼の彼女に対する慈愛の情が伝わってくる。
だが、どちらかといえば(これはわたしの勝手な想像であり、願望でもあるが)、モリゾはマネにとって愛おしくも、犯しがたい女性であり、画家としても尊敬すべき相手だったのではないだろうか。 二人の関係がプラトニックなものにとどまっていたからこそ、モリゾはマネの弟、ウジェーヌと結婚して幸せな家庭を築くことができたし、ウジェーヌも彼女の夫として、そしてモリゾの絵の最大の理解者として、結婚後も彼女の創作活動を応援し続けたのではないだろうか。
いずれにしろ、モリゾは裕福で満ち足りた家庭生活を送りながら、自分の姉や娘をモデルにした温かみのある作品を数多く残している。
いっぽう、マネが最も愛したもうひとりのモデル、ヴィクトリーヌ・ムーランも画家を志し、1876年にはサロンに入選するが、その後は酒に溺れ、困窮した生活を送ったという。 なんとなく「モンパルナスのキキ」ことアリス・プランを髣髴とさせるエピソードだ。 時代を切り拓いた芸術家のミューズたちの悲しい末路。 だからこそ、朽ちて滅びていく前のその煌めく姿を映しとった作品――画家が切り取ったモデルの人生の一瞬のかけら――には、名状しがたいある種の生命力のようなものが宿っているのかもしれない。 (つづく)
2010年7月27日火曜日
ポーの『大鴉』(マラルメ訳)の挿絵
美術館の廊下の天井。
各展示室をつなぐクラシカルな廊下。
(前回からのつづき)
第Ⅱ部は「親密さの中のマネ:家族と友人たち」。
ボードレールやエミール・ゾラ、エドガー・アラン・ポー、マラルメなど、社交的で才能あふれるマネの幅広い交友関係を伝えるコーナーだった。
非常に興味深かったのが、マラルメが仏訳したポーの詩『大鴉』の挿絵である。
ポー、マラルメ、マネという超豪華メンバーによるこの超豪華仏訳書は、現在60部の現存が確認されており、1部(なんと!)1500万円ほどの値がつくこともあるという。
この本の出版秘話については『マラルメの「大鴉」―エドガー・A・ポーの豪華詩集が生れるまで 』(バックナム著、柏倉康夫訳著)に詳しい。
版元社長兼編集者の書簡にもとづいて編集されたこの本には、締め切りをちっとも守らない訳者(マラルメ)および画家(マネ)に泣かされ、書評で酷評され(直訳調だったらしい)、さっぱり売れないまま、刊行の1年半後に版元が破産するというドタバタ悲劇がつづられている。
ちなみに日本にも日夏耿之介訳、ギュスターヴ・ドレ挿画という、仏版に勝るとも劣らない豪華な『大鴉』が存在する(薔薇十字社版、出帆社版などいくつかの版があるが、最近では2005年に沖積舎から刊行されている。『院曲サロメ』もそうだけど、こういう復刻はうれしい限り)。 (つづく)
各展示室をつなぐクラシカルな廊下。
(前回からのつづき)
第Ⅱ部は「親密さの中のマネ:家族と友人たち」。
ボードレールやエミール・ゾラ、エドガー・アラン・ポー、マラルメなど、社交的で才能あふれるマネの幅広い交友関係を伝えるコーナーだった。
非常に興味深かったのが、マラルメが仏訳したポーの詩『大鴉』の挿絵である。
ポー、マラルメ、マネという超豪華メンバーによるこの超豪華仏訳書は、現在60部の現存が確認されており、1部(なんと!)1500万円ほどの値がつくこともあるという。
この本の出版秘話については『マラルメの「大鴉」―エドガー・A・ポーの豪華詩集が生れるまで 』(バックナム著、柏倉康夫訳著)に詳しい。
版元社長兼編集者の書簡にもとづいて編集されたこの本には、締め切りをちっとも守らない訳者(マラルメ)および画家(マネ)に泣かされ、書評で酷評され(直訳調だったらしい)、さっぱり売れないまま、刊行の1年半後に版元が破産するというドタバタ悲劇がつづられている。
ちなみに日本にも日夏耿之介訳、ギュスターヴ・ドレ挿画という、仏版に勝るとも劣らない豪華な『大鴉』が存在する(薔薇十字社版、出帆社版などいくつかの版があるが、最近では2005年に沖積舎から刊行されている。『院曲サロメ』もそうだけど、こういう復刻はうれしい限り)。 (つづく)
スペイン趣味とレアリスム:1850-60年代
(前回からのつづき)
第Ⅰ部は「スペイン趣味とレアリスム:1850-60年代」。
この時期マネは、当時流行していた「スペイン趣味」の洗礼を受け、スペイン的な主題を描いた作品を数多く残している。
特に印象深いのが『死せる闘牛士』http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=3840や『闘牛』
http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=3780 などの闘牛シリーズ。
1965年秋、ゴヤやエル・グレコ、ベラスケスら巨匠たちの作品を見るために、マネは単身スペインを訪れたが、スペインの風土と食事が合わなかったため、わずか10日間でパリに戻っている。その間、闘牛場に何度か足を運んではスケッチにいそしみ、帰国後には、それをもとに残虐かつドラマティックな闘牛シーンの作品を描いた。
マネが描く闘牛場のシーンは、スペイン特有のあのギラつく日射しと、観客席から立ちのぼる血に餓えた興奮と熱狂、死と栄誉の狭間で敗れた闘牛士の無残な骸(むくろ)が強烈な対比として描かれている。
いっぽう、『死せる闘牛士』は、もとは『闘牛場での出来事』という群像を描いた作品を、闘牛士の骸だけを切り離したもの(切り離されたもう片方の作品には、まるで闘牛士が復活したかのように、緊迫した闘牛シーンが描かれ、別の作品として仕上がっている)。
人々の興奮や欲望、憤る牛といった「動」の部分をすべて取り除いた『死せる闘牛士』の画面を支配するのは、完全なる「静」であり、厳粛な死の世界である。 肩幅が広く、胸板の厚い、まだみずみずしい充実した肉体を感じさせるその屍は、一瞬をついて訪れた「死」という厳然たる現実を際立たせている。
*******
この時期マネは、お気に入りのモデルのひとり、ヴィクトリーヌ・ムーランと出会う。
1862年、最高裁判所前の広場の人ごみのなかで、マネは不思議な魅力を持つひとりの女性に目を留めた。以来、マネが引き出したヴィクトール・ムーランの強烈な個性と、マネの斬新な画風と色彩感覚とが相まって、『草上の昼食』(1863年)や『オランピア』(1865年)など、時代を象徴するセンセーショナルな名画が次々と生み出されていった。
今回の展覧会では、(パンフレットの表紙画にも使われているように)ベルト・モリゾがヒロインとなっているため、ヴィクトリーヌ・ムーランは脇役に徹しているというか、ムーランがモデルになっている作品は少なかった。
そんななか、珍しく、それほどスキャンダラスではない画題で描かれていたのが、『街の女歌手』だ。http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=3857(この画像では赤っぽく写っているため、原画の見事な色彩が映し出されていないのが残念。)
この絵はもともとマネが、ひとりの女性を街角で見かけて、モデルになってほしいと声をかけたが断られたために、ムーランが代わりを務めたものだが、着衣のムーランをモデルにした絵のなかでは最も美しい作品だと思う。
黒い背景のなかに浮かぶ、暗く渋い緑のドレス。 ドレスの黒い縁取りと、黄色い包み紙、ルビーのように赤いサクランボが、じつに効果的に配され、ムーランの意志の強そうな個性的な顔立ちを引き立たせている。マネの絶妙な色彩感覚を物語る一枚だ。
このコーナーには、マネの日本趣味が存分に生かされた『エミール・ゾラ』http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=3812 や、気球や大道芸人など、いかにも19世紀後半のパリらしい風物を描いたエッチングやリトグラフ、淡彩画も展示されていた。 (つづく)
第Ⅰ部は「スペイン趣味とレアリスム:1850-60年代」。
この時期マネは、当時流行していた「スペイン趣味」の洗礼を受け、スペイン的な主題を描いた作品を数多く残している。
特に印象深いのが『死せる闘牛士』http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=3840や『闘牛』
http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=3780 などの闘牛シリーズ。
1965年秋、ゴヤやエル・グレコ、ベラスケスら巨匠たちの作品を見るために、マネは単身スペインを訪れたが、スペインの風土と食事が合わなかったため、わずか10日間でパリに戻っている。その間、闘牛場に何度か足を運んではスケッチにいそしみ、帰国後には、それをもとに残虐かつドラマティックな闘牛シーンの作品を描いた。
マネが描く闘牛場のシーンは、スペイン特有のあのギラつく日射しと、観客席から立ちのぼる血に餓えた興奮と熱狂、死と栄誉の狭間で敗れた闘牛士の無残な骸(むくろ)が強烈な対比として描かれている。
いっぽう、『死せる闘牛士』は、もとは『闘牛場での出来事』という群像を描いた作品を、闘牛士の骸だけを切り離したもの(切り離されたもう片方の作品には、まるで闘牛士が復活したかのように、緊迫した闘牛シーンが描かれ、別の作品として仕上がっている)。
人々の興奮や欲望、憤る牛といった「動」の部分をすべて取り除いた『死せる闘牛士』の画面を支配するのは、完全なる「静」であり、厳粛な死の世界である。 肩幅が広く、胸板の厚い、まだみずみずしい充実した肉体を感じさせるその屍は、一瞬をついて訪れた「死」という厳然たる現実を際立たせている。
*******
この時期マネは、お気に入りのモデルのひとり、ヴィクトリーヌ・ムーランと出会う。
1862年、最高裁判所前の広場の人ごみのなかで、マネは不思議な魅力を持つひとりの女性に目を留めた。以来、マネが引き出したヴィクトール・ムーランの強烈な個性と、マネの斬新な画風と色彩感覚とが相まって、『草上の昼食』(1863年)や『オランピア』(1865年)など、時代を象徴するセンセーショナルな名画が次々と生み出されていった。
今回の展覧会では、(パンフレットの表紙画にも使われているように)ベルト・モリゾがヒロインとなっているため、ヴィクトリーヌ・ムーランは脇役に徹しているというか、ムーランがモデルになっている作品は少なかった。
そんななか、珍しく、それほどスキャンダラスではない画題で描かれていたのが、『街の女歌手』だ。http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=3857(この画像では赤っぽく写っているため、原画の見事な色彩が映し出されていないのが残念。)
この絵はもともとマネが、ひとりの女性を街角で見かけて、モデルになってほしいと声をかけたが断られたために、ムーランが代わりを務めたものだが、着衣のムーランをモデルにした絵のなかでは最も美しい作品だと思う。
黒い背景のなかに浮かぶ、暗く渋い緑のドレス。 ドレスの黒い縁取りと、黄色い包み紙、ルビーのように赤いサクランボが、じつに効果的に配され、ムーランの意志の強そうな個性的な顔立ちを引き立たせている。マネの絶妙な色彩感覚を物語る一枚だ。
このコーナーには、マネの日本趣味が存分に生かされた『エミール・ゾラ』http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=3812 や、気球や大道芸人など、いかにも19世紀後半のパリらしい風物を描いたエッチングやリトグラフ、淡彩画も展示されていた。 (つづく)
2010年7月26日月曜日
Manet et le Paris moderne
19世紀末にコンドルが設計した煉瓦造りのオフィスビル、
『三菱一号館』を忠実に再現した美術館の外観。
内装も忠実に再現されたエントランスロビーの扉飾り。
弥が上にも期待が高まる。
(つづく)
登録:
投稿 (Atom)